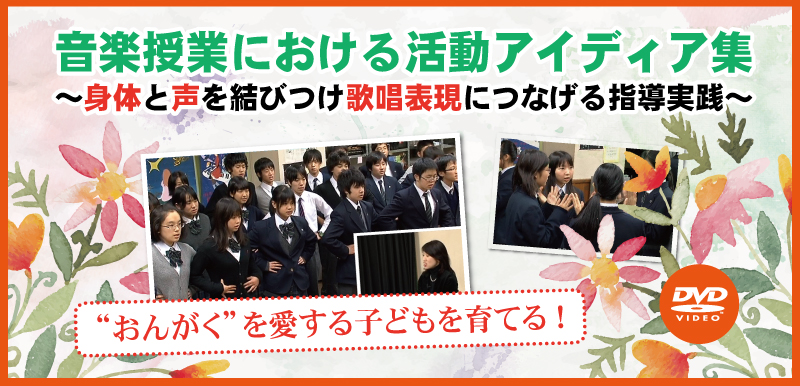【第6回】生涯音楽を楽しめる力を育む~自然の音に耳をすませて~

第6回
「生涯音楽を楽しめる力を育む
~自然の音に耳をすませて~」
2017年1月28日
皆さま、お久しぶりです。お元気でお過ごしでしょうか。渡辺行野です。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
昨年度は、「ゆきの先生の音楽室」コラムをお読み頂き、ありがとうございました。
1月から、またコラムが始まりますので、引き続き宜しくお願い致します。
「自分なりの音楽」を身に付けるために
さて、先日、このコラムを掲載してくださっているジャパンライムの方々とお会いし、お話した際に、それぞれの学生時代の話になりました。
「昔、自分が受けた教育というものは、良いにせよ悪いにせよ、なぜかとてもよく覚えている」という話になり、義務教育における時間の大切さなどの話で盛り上がりました。
また、その際、“音楽”に対する思い出があまり良くないものとして自分の記憶に残っていたとしても、「何故か、“音楽”には今も惹かれる、また音楽をしたいという欲求が湧く」などの話も出て、“音楽”ってやはりすごい!音楽の持つ力は不思議!などということが話題に上がりました。
確かに、幼少期から大人になるまでの経験や体験という学習活動を通して、無意識のうちに身体にしみ込んでいた部分があるのでしょう。
言い換えると、学校での教育活動を通して、「自分なりの音楽」という力を身に付けさせていくことが肝要なのではないでしょうか。
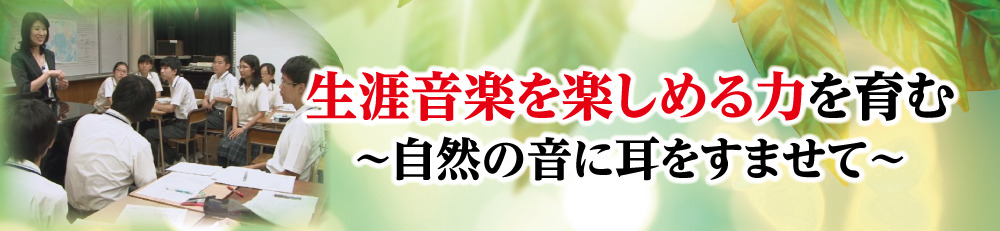
生活の中には、多くの音が存在しています。
音があることが当たり前の日常に存在していること、その感覚に着目していくことも大事になってきますね。
忙しくて、耳を研ぎ澄ます時間も少ないように思います。
意識して、聴こうとしないと聴こえてこない音もあるように感じます。
音の原点、音楽のルーツ、音楽が持つ意味など、
指導者としてもう一度立ち止まり、原点に戻る、自分を振り返ってみることも大切ですね。
身の回りの音、生活音や環境音、自然の音、
私たちはどれくらいの音を聴き取り、感じ取っているのでしょうか。
さて、これは学校などにある自然の風景ですが、
皆さんには、どんな音が聴こえてきますか?


「音」の存在、「音」が生まれる前の「沈黙」、「無の時間」、
そこから音が生まれる瞬間・・・
たまには、耳を研ぎ澄まし意識的に音を感じてみる。
音楽を指導する者として、そんなことも大切にしていきたいですね。
これからのコラムでは、「音楽とは何だろう…?~もう一度原点に戻る~」などの「つぶやき」や、
「皆さんのお悩み相談」、そして皆さんの抱えているお悩み相談の内容に通じる
「音楽科教育の在り方や重要性」、さらには、「音楽を通して学ぶこと」などなどを、
皆さんとご一緒に追い求めていけたら幸いです
小中高の校種にて教鞭をとり、各発達段階における豊富な指導実績を持つ。数々の授業実践の中で、幅広い音楽領域(歌唱・鑑賞・創作・器楽・伝統音楽など)の研究を進めている。歌唱・鑑賞教育を重視し、人間教育と関連させた音楽科教育や、小中連携研究のカリキュラム作成など様々な研究で業績を残している。また、前作のDVD「“おんがく”を愛する子どもを育てる!音楽授業における活動アイディア集」では、楽しみながら無理なく力をつけていく指導方法が支持され、好評を博した。雑誌『教育音楽』にも寄稿。2016年から、文京学院大学児童発達学科の助教に就任し、保育士・幼稚園教諭・小学校教諭の養成に力を注いでる。
☆渡辺先生の音楽授業は、こちらのDVDに収録されています☆